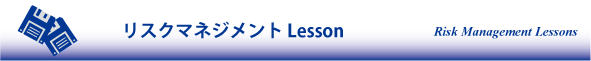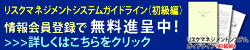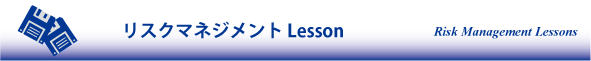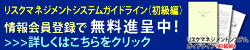| |
◆規制緩和 ◆グローバル化 ◆社会的責任の要請 ◆情報技術の革新
◆メインバンク制度崩壊 ◆雇用形態の変化 ◆気象の変化
◆法的要請 |
| |
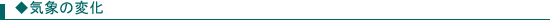 |
 |
| 近年、「観測史上初の猛暑」や「観測史上初の大雨」といったニュースを耳にします。地球温暖化や森林の破壊などが原因との解説もありますが、これから世界の気象はどうなるのでしょう?気象庁では、異常気象を「過去30年の気候に対して、著しい偏りを示した気候」と定義しています。つまり、近年の気象のように、徐々に平均温度が上がっている場合は、異常気象とは呼びません。 |
| |
| ◆異常気象とは? |
 |
異常気象とは、平均を著しく上回る、または下回る気象の際に用います。
-
近年の異常気象が温暖化の影響か否か?-
この問題は学者により意見が異なるようですが、実際に自然災害により損害が発生しているのは事実なわけですから、このリスクに対応する必要があります。 |
| |
| ◆自然災害への対策 |
 |
| 日本では、自然災害のリスクを考える際、人命に一番影響のある「地震」が対象となることが多いですが、世界の気象が大きく変動している現在、大雨による水害や、長期間の猛暑、台風、雷といった気象に対しても対応する必要があります。 |
| 自然災害への対策は、業務の継続を目的とした「事業継続計画」が必須となりますが、全社的リスクマネジメントを対象とした場合、いわゆる災害対策だけではありません。企業の売上に影響を及ぼす可能性のある気象変化、例えば飲料製造業では、猛暑、冷夏が売上を大きく左右しますし、暖冬であれば衣料製造業の売上に影響します。また、海外で異常気象が発生することにより、部品や原材料が入荷されず製品製造に大きな影響を与えるサプライチェーン・リスクが顕在化する可能性もあります。 |
| |
| 気象に係るリスクのように、その発生確率を低減できないリスク要因に対しては、やはり「情報収集」と平常時の準備が重要な鍵となります。どのような異常気象の場合に、どのような影響、損害が発生しているか(他社の事例を含め)。ある米国大手IT企業では、リスクマネジメント部部員8名のうち2名は、常に世界中で発生している事件、事故の情報を収集し、それらが自社で発生した場合どのように対応することになっているかのシミュレーションを常に行っているそうです。 |
| |
| |