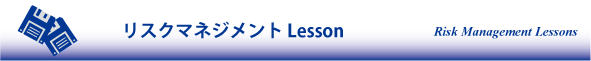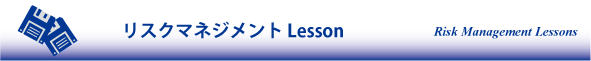| |
| ◆ 緊急事態発生時のマニュアル ◆ エスカレーション・ルール |
| |
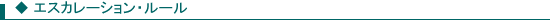 |
 |
緊急時対応として平常時から準備する必要がある対策に、エスカレーション・ルールがあります。
エスカレーション・ルールとは、非正常事象が発生した際、迅速な情報収集と対応指示を行うため、どのような事態になったら、どのルートでどのレベル(役職)まで報告するか、誰が責任者となるのかを定めておくことです。 |
| |
| 不祥事やクレームは、小さな非日常的事象が大きな問題へと発展することがよくあります。経営者や管理職は、問題が拡大した段階で「なぜもと早く報告しなかったのか」と部下を叱る姿を目にしますが、現場担当者は視点の違いから判断を誤ることが多々あります。さらに、上司の手を煩わせない事がサラリーマンとしての役割のような錯覚に陥っている若手社員も多いようです。 |
| |
| 経済産業省の実践テキストでは、図表のように緊急時のレベルを3段階にわけ有事それぞれの程度、該当する有事の例、責任者を明確にしています。 |
| |
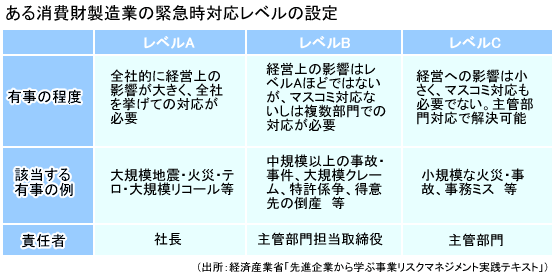 |
| |
| 実際の現場では、有事の程度をさらに明確にすることが望まれます。例えば、食品メーカーであれば、同様のクレームが1時間に3件以上あった場合や製造ラインが1時間以上停止する場合など、可能な限り数値で報告義務ラインを設定するとアルバイトなどの非正規雇用者に対してもわかりやすくなります。 |
| |
| 非日常的事象の第一報は不完全な情報であっても、迅速さが大切です。食品業界などでは情報の伝達が1時間遅れると数百人、数千人単位の被害者が発生する恐れがあります。情報伝達を迅速に行うためには、有事の際誰に報告すれば良いのか?その人がいない場合は誰か?という報告の選択肢を、優先順位を付け3つ以上準備する必要があります。 |
| |
| また、もう一つ大切なこと―それは後に誤報だとわかった場合でも、その通報者を絶対に責めない事も予めルールとして決めておくことです。このルールが無いと社員の戸惑いを誘発するばかりか、肝心な会社としての対応が大幅に遅れる恐れがあります。 |
| |
雪印乳業で大規模食中毒事件を分析すると、エスカレーション・ルールの重要性が良く理解できます。
・大樹工場で3時間停電した際、誰がどのレベルの責任者まで連絡すれば良かったのか?
・お客様コールセンターで消費者からのクレームが入り始めた時、どの段階で食中毒と判断すべきだったのか?
・その判断は誰が行うべきだったのか?
・日本人は牛乳でお腹を下すことが多いとの理解であるなら、何を基本に異常事態と判断するのか?
日本の企業では、「阿吽の呼吸」を価値とし判断基準が明確になっていない事が多数存在します。緊急時対応における判断基準は、可能な限り平常時に決定しておくことをお勧めします。 |
| |
| |
| 次のページへ → |
| |
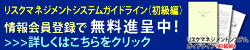 |
| |
| 【リスクマネジメントレッスン‐目次‐】 |
 |
| | 1.進化するリスクマネジメント | 2.リスクマネジメントの必要性 | 3.リスクの認識 | |
 |
| | 4.リスクマネジメント・プロセス | 5.リスクの評価・査定 | 6.リスクの管理・対策 | |
 |
| | 7.リスク・チェーン | 8.BCP(事業継続計画) | 9.緊急時対応 | |
 |
| | 10.リスクファイナンス | 11.モニタリング | 12.リスクに強い組織体制 | |
| |